|
|
|
1.貸借対照表を簡素化して見る
決算書を読むことは、特に難しいことではありませんが、
現実には「決算書が読めない、決算書の分析ができない」
経営者の方も多いのではないでしょうか?
自社を健全経営に導くためには、管理会計の導入が不可欠ですが
決算書がわからなければ、管理会計へ進むことができません。
このためには、先ず決算書を理解してください。
損益計算書に比べて、貸借対照表は取っ付きにくいものだと思います。
馴染みのない科目が、並んでいるせいでしょうか?
資産の部(貸借対照表の左側)では、
立替金・前払費用・長期前払費用なども分かりずらい科目名です。
また、何が建物付属設備で、何が構築物なのかも、良く分からないかも知れません。
あるいは、有形固定資産、無形固定資産、投資など。
また、負債の部(貸借対照表の右側)では、前受金や仮払金もそうでしょうか。
消費税も、仮払とか仮受とか、未払消費税も出てきます。
もちろん、それぞれに意味がありますので、どうでも良いとは言いません。
しかし、貸借対照表と友達になるためには、思いきって簡素化して見ましょう。
次の表は、ある会社の貸借対照表を極限まで簡素化したものです。
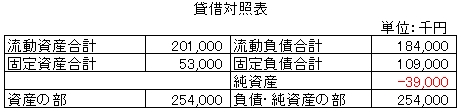
どうですか、たったこれだけです。
合計では、254,000で、左側と右側が同じ金額でバランスしています。
だから、英語では貸借対照表を、バランス・シートと言います。
それぞれの意味ですが
流動資産とは、1年以内に現金化可能な資産。
固定資産とは、流動資産以外の資産。
流動負債とは、1年以内に支払わなければならない負債。
固定負債とは、流動負債以外の負債。(中小企業では通常長期借入金です)
そして
純資産=資産合計-(流動負債+固定負債)
となる訳です。
この会社の場合は、純資産がマイナスになっています。
いわゆる、債務超過状態です。。
それで、経営とは、この純資産を増加させていくことなのです。
内部留保・自己資本を増加させるために、何をすべきかが経営なのです。
経営目的は、すごく単純なことに気が付きますね。
ここまでは、簡単に理解できたと思います。
それでも、これだけでは分析できません。
そこで、次にそれぞれの内訳表を作成して見たいと思います。
2.貸借対照表とは、どこから資金を調達してどこに使われたかを見るもの
貸借対照表で真っ先に見たいところは、固定資産と固定負債です。
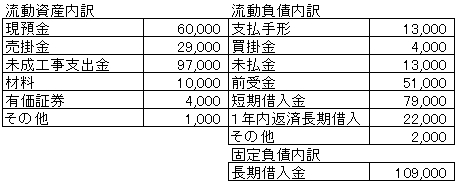
支払能力分析のひとつとして、固定長期適合率があります。
これもまた取っ付き難い名前ですが、とりあえず公式を書いて見ましょう。
固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)
で求められます。
その前に、固定負債の内訳を見ると、全額長期借入金(109,000)です。
また、流動負債内訳で、1年内返済長期借入が22,000とあります。
これを、固定負債に戻して考えると
長期借入金残高は109,000+22,000=131,000となるので
この会社の固定長期適合率は
53,000÷(-39,000+131,000)=57.6%となります。
たぶん、経営分析の書籍などを見れば、
「固定長期適合率は小さい方が良いとか、100%以下が望ましい」
などと書かれているはずです。
理由は、長期間で減価償却する固定資産は、長期借入金で賄うべきで
この比率が100%を超えている時は、短期借入金、つまり運転資金で
固定資産を購入しているので資金繰りが、大変になる。
なるほど、ごもっともな理由であり、私もその通りであると思います。
これに従えば、57.6%と言う結果は、望ましいと判断されてしまいます。
しかし、この会社場合、53,000の固定資産に対し、長期借入金が、131,000。
では、差額の78,000はどこに行ってしまったのか?
見成工事支出金(工事完了前に支出された分で売上は未計上)が、97,000。
前受金(工事完了前に先に受け取った分)が、51,000で、
この差額が、46,000あります。
また純資産が39,000のマイナスになっています(債務超過)。
この合計85,000のほとんどが、
長期借入金で賄われていると考えることもできます。
このうち、純資産のマイナス分が、赤字の穴埋めとして使われた訳です。
ところが、流動資産の内訳で、短期借入金が79,000あります。
見成工事支出金と前受金の差額46,000は、本来こちらで賄っているはずです。
ここで、疑いが生じます。
一概には言えません、こんなケースもあり得るでしょうから。
私の見解としては、
見成工事支出金と前受金の差額が大きすぎるのでは?
もしかしたら、
見成工事支出金を水増し計上しているのではないか?
そうであるならば、立派な粉飾決算です。
さて仮に、
支払手形・買掛金・未払金の全額を短期借入金で賄ったとして、30,000。
見成工事支出金と前受金の差額が、46,000。
30,000+46,000=76,000となり、
十分に、短期借入金79,000で賄えきれるはずです。
これにしたって、売掛金が29,000あるので、
支払手形・買掛金・未払金の全額を、借入金で賄う必要はないはずです。
ここで、また疑いが生じます。
回収不能売掛金があるのでは?と。
いろいろな疑念を無視しても
長期借入金-(固定資産+赤字の穴埋め)
=131,000-(53,000+39,000)
=39,000はどこに行ってしまったのでしょうか?
すると、現預金が60,000あります。また、有価証券が4,000あります。
借入金は、こちらに回っていると考えることができます。
このことは、中小企業向け緊急保証制度などを利用して、
金融機関から借りまくった結果であると考えて良いでしょう。
では、この会社ですが、長短合わせて210,000の借入金は、借り過ぎなのか?
表にはありませんが、年間の減価償却は2,000、利益は0でした。
必要利益とは、資金繰りを楽にする利益とも言えますが、
会社が健全に回っていくためには、次のようになっている必要があります。
必要利益>(長期借入金元金返済額+納税額-減価償却費)
これに当てはめると、年間20,000のお金が、また不足することになりますが、
今のところ現預金が60,000あるので、業績がこれ以上悪化しない限り
来期は、何とか会社は回って行くでしょう。
そして、現状では借入して良かった、と言わざるを得ません。
まだ、1年、2年は大丈夫そうですから。
このように、貸借対照表を見ることで、
他社であっても、ある程度の分析が可能になります。
また、単純に、流動比率とか、
売上債権/支払債務比率だけの分析も意味がありません。
今回のような切り口で、総合的に判断するのが望ましいでしょう。
今回のような切り口とは
①どこからどんなお金を調達しているのか
②そのお金はどこに使われているのか
を見ることから、貸借対照表を読んで見ましょう。
と言うことです。
自社のことであれば、もっと良く分かるはずです。
そして、私が示したように
決算書の貸借対照表を思い切って簡素化し、内訳表を作れば
とても見やすくなり、B/Sアレルギーもなくなるでしょう。
さて、結論ですが、
貸借対照表から、この会社は健全であるとの判定はできません。
一刻も早く、借入金依存体質から脱却しなければなりません。
経営改善・経営革新は待ったなしのところに来ています。
戦略を見直し、経営体質の改善を推し進め、健全経営に舵を切るべきです。
なお、この会社の場合、1年や2年で健全な状態へ持ちこむことは無理でしょう。
5年なりの中期経営計画を立案し、確実に計画を達成して行くしかありません。
そためには、管理会計を導入して、経営計画に命を吹き込む必要があります。
また、管理会計の導入は、収益性の向上をもたらします。
そのためには、管理会計ツール【ここをクリック】が不可欠です。
決算書を理解し、管理会計を実践し、健全経営を目指しましょう。
さて、次回は損益計算書の読み方についてです。
貸借対照表をあまり見ない経営者の方でも、損益計算書は毎月チェックしていると思います。
しかし、もっと損益計算書が理解できる方法を、お伝えします。
|
|
|