|
|
|
1.資金繰りが苦しい状態が続くと最悪倒産に至ります
会社が存続するためには、健全な会社でなければならない。
↓
健全な会社になるためには、自己資本を充実させなければならない。
↓
自己資本の充実のためには、ほんとうの会社の利益、必要利益を獲得しなければならない。
そして、自己資本を増加させる必要利益を獲得するためには、
【獲得利益>借入金元金返済額+納税額−減価償却費】
となっていなければならない。
これが出来ない会社は資金繰りが苦しくなり、
やがて債務超過に転落する可能性があります。
↓
債務超過になれば銀行からの融資も難しくなり、全く資金手当てができなくなります。
↓
資金手当てができなくなれば、給料や買掛金の支払いができなくなり
支払手形を振り出していれば、不渡り手形になり銀行取引が中止されます。
↓
銀行取引が中止されれば、会社の行く末は倒産と言う事になってしまいます。
自己資本の充実こそが
資金繰り問題から解放され、企業を健全経営へと導き、倒産しない唯一の道なのです。
2.資金繰りの悪化は支払能力の低下
健全経営・資金繰りの問題を、別の視点から見て行こうと思います。
会社を危険な状態に置かないためには、資金が順調に回っていく必要があります。
資金繰りの悪化は、言いかえれば支払能力の低下と言う事になります。
それでは、以下の貸借対照表を参考に、支払能力の善し悪しを判断して見ましょう。
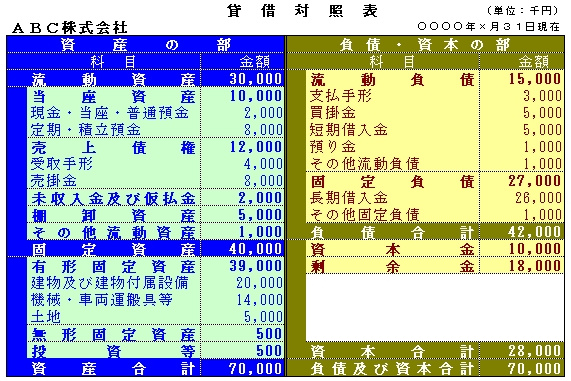
流動比率から支払能力を見る
一年以内に現金化する流動資産と、
一年以内に返済、または、支払わなければならない流動負債
のバランスを見る。
流動比率=流動資産÷流動負債
(流動資産:現金・預金・売掛金・受取手形・棚卸資産など)
(流動負債:買掛金・未払金・支払手形・短期借入金など)
流動比率が高いほど資金繰りが楽になります。
当然、流動負債が多くなれば資金繰りは苦しくなります。
150%以上あれば良しだが、200%くらいあれば安心でしょう。
この比率が低下している原因は、
・買掛金や短期借入金の増加
・運転資金で設備資金を賄っている
対策は、
・短期借入金から長期借入金に変更する
また、次の場合比率が良好でも、資金繰りは苦しくなってしまいます。
・受取手形のサイトが長く、支払手形のサイトが短い
・過剰在庫か不良在庫の発生
対策は、
・受取手形決済期間を短縮する
・支払手形決済期間を延長する
・在庫管理を徹底する
当座比率から支払能力を見る
流動資産のうち換金性の高い当座資産と、流動負債のバランスを見る。
当座比率=当座資産÷流動負債
換金性の高い流動資産=当座資産とは、
現金・預金・売掛金・受取手形・短期貸付金・一時所有の有価証券など。
当座比率が高いほど資金繰りが楽になります。
当然、流動負債が多くなれば資金繰りは苦しくなります。
80%以上あれば何とか、でも、100%以上が望ましいと思います。
この比率が低下している原因は、
・過剰在庫を抱えている
・拘束性預金(借入金の担保預金のため使えない)がある
・焦げ付き債権がある
対策は
・在庫を削減する
・短期借入金から長期借入金に変更する
・顧客の与信管理を冷静に判断する
売上債権/支払債務比率から支払能力を見る
代金の回収と支払、つまり、受取勘定と支払勘定のバランスを見る。
売上債権/支払債務比率=売上債権÷支払債務
在庫と現金・預金を除いた運転資金がどうなっているのかが分かります。
100%以下であればまず問題ないが
それ以上になると、資金手当てが必要になってきます。
この比率が高くなる原因は、
・売上の増加が続いている
・売上の季節変動が大きい
・突然大量受注が発生した
売上が増大すれば、債権(売掛金・受取手形)、債務(買掛金・支払手形)
ともに増加することになります。
特に、債務の支払の方が債権回収より早い場合、その時間差のため、
売上好調にもかかわらず、資金繰りが苦しくなってしまうのです。
対策は
・銀行から短期運転資金を調達する
(これは、増加運転資金といい、銀行は容易に融資に応じるので心配ない)
反対に、売上が減少の場合にも比率が良くなるので、この場合は要注意です。
固定長期適合率から支払能力を見る
自己資本と他人資本あわせて、どれくらい固定資産に使われているかを見る。
(他人資本とは固定負債のこと)
固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)
自己資本だけで固定資産を賄うのが理想ですが、
中小企業でなくとも、自己資本だけでは足りないのが多くの企業の現状です。
比率は小さければ小さいほど良い。ただし、100%を超えたら問題です。
この比率が高くなる原因は
・長期借入金による設備投資
対策は
・自社の返済限度額内で長期借入金を調達する
返済限度額とは、利益−納税額+減価償却費の範囲内で返済できる額のことです。
ちなみに、採算割れと、良く言いますが、
ほんとうは、この範囲を超えた場合のことを言うのです。
返済限度額を超えると、当然、長期借入金の返済に行き詰ってしまいます。
まだ手形の問題など他にもありますが、支払能力を見るためには、
取りあえず、この四つの指標を気にして欲しいと思います。
企業は売上が増加しているから、黒字だから、安泰ではありません。
支払能力を見極め、突然資金繰り難にならないために、
以上の指標から対策を講じることが大切です。
3.指標を使わずとも資金繰り悪化・倒産の兆候が分かります
次にような傾向が見られた、すでに会社は危険な状態にあるで判断できます。
・粉飾決算をしてしまった(在庫・仕掛の水増し計上、架空売上の計上)
・借入金の返済が遅れがちになってきた
・買掛金や未払金の支払いのための支払手形の期日を長くしたか、支払が遅れている
・納税資金や賞与資金を借入しないと支払えない
・資金繰りが頭から離れず、仕事に打ち込めない
・銀行が融資に応じない
・役員からの借入金が増えてきた
(社長の個人預金を取り崩すか、役員報酬を受け取っていないという意味)
どれか思い当たる節があれば、必ず
流動比率=流動資産÷流動負債
当座比率=当座資産÷流動負債
売上債権/支払債務比率=売上債権÷支払債務
固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)
の指標が悪化しているはずです。
資金繰りの問題を支払能力の視点から見てみました。
企業は金=キャッシュが回っているうちは倒産しません。
黒字でも金=キャッシュが回らなくなると倒産してしまう場合もあります。
資金繰り改善の基本は自己資本の充実ですが
自社資金繰りや支払能力が悪化している時は、早めの資金対策が必要になります。
資金繰り悪化⇒自己資本減少⇒債務超過の悪循環に陥らないために最初に把握することは、
予算作成プログラム【ここをクリック】により必要利益の獲得と、
自己資本の増加を可能にする予算を作成する必要があります。
|
|
|